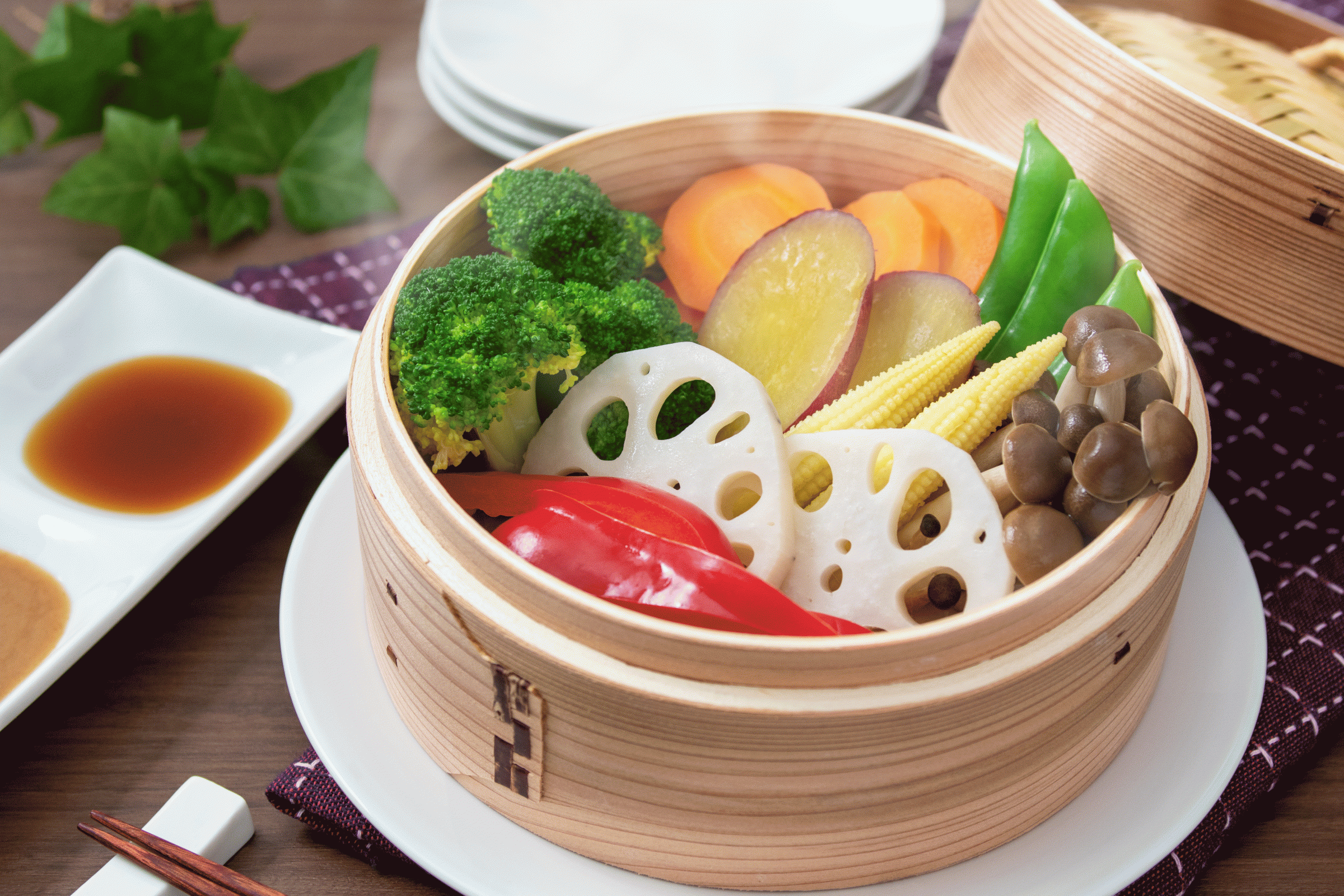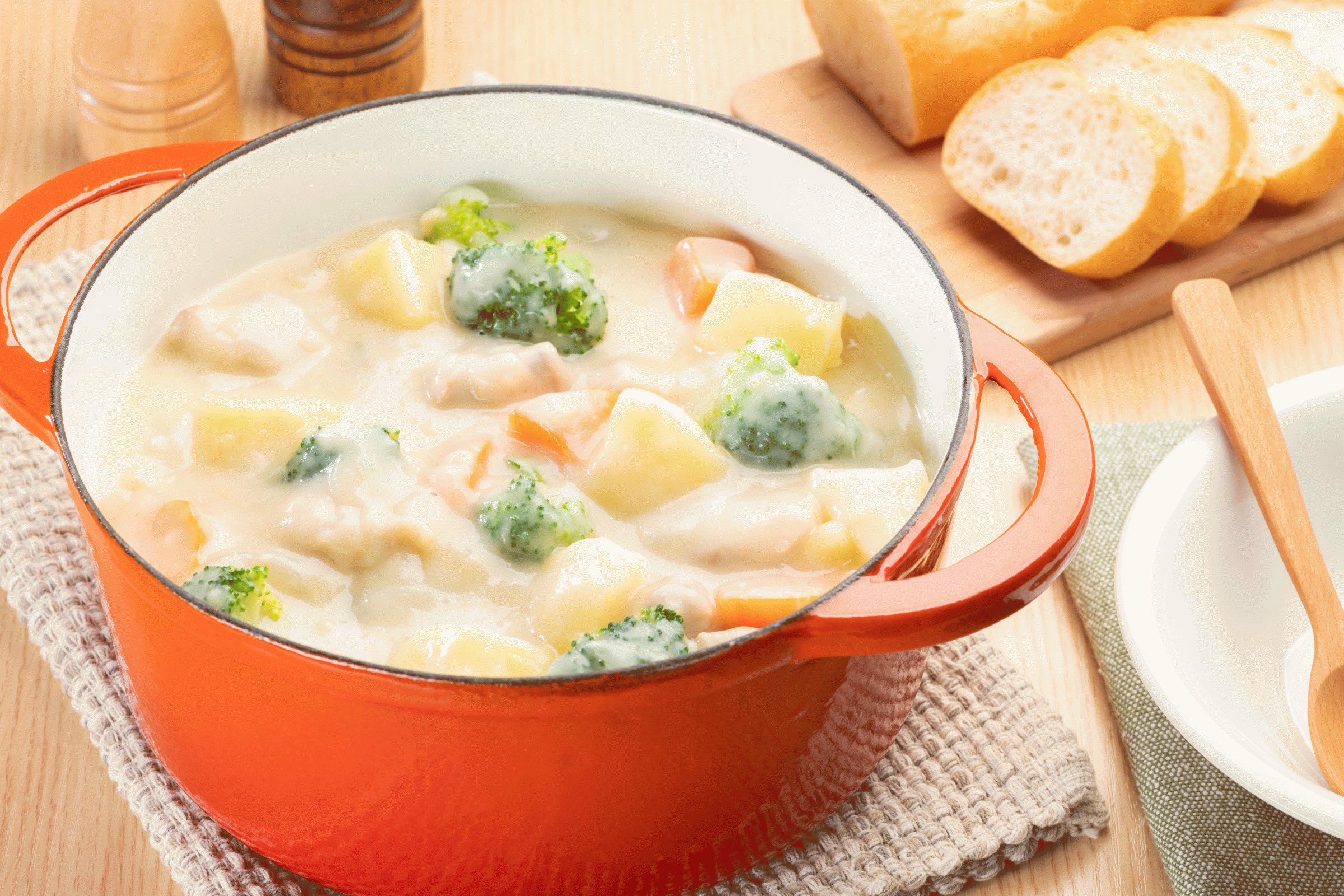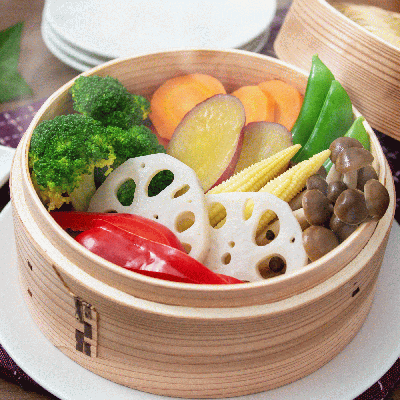
食事
冬に負けないからだをつくる「冬野菜」のすすめ
2025.10.17
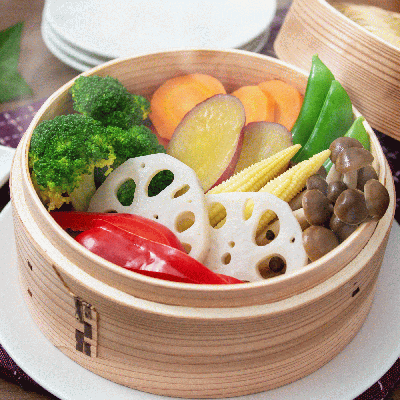
最近は秋を楽しむ暇もなく、急に気温が下がって冬のような寒さが訪れることが多くなりました。寒さが増してくると、からだが冷えて体調を崩しやすくなることも。寒さに備えるために、日々の食事に取り入れたい“冬野菜”について紹介します。
プロフィール

株式会社タニタ 管理栄養士 本橋 昌子
人々の健康をサポートできるような仕事がしたいと思い、2023年11月に中途入社。企画職として、キャラクターをはじめとしたコラボ商品や新商品の企画立案などを行っている。
冬野菜とは?
名前の通り、冬に旬を迎える野菜のことで、にんじん、大根、れんこん、ごぼう、かぶ、白菜、ほうれん草、ブロッコリーなどがあります。大きな特徴は、冬の寒さに耐えるために、細胞にでんぷんや糖を蓄えること。冬野菜は甘くておいしい、と感じたことがある人も多いのではないでしょうか。
冬野菜に多く含まれるビタミンC(大根、かぶ、ほうれん草、ブロッコリーなど)やβ-カロテン(にんじんなど)は、免疫力の維持に役立つといわれています。また、食物繊維(ごぼう、れんこんなど)は腸内環境を整え、からだの調子をサポートする働きが期待できます。
冬野菜が「からだを温める」といわれる理由
食後、からだがぽかぽかと温まる感覚がありますよね。これは、食物を消化するときに発生する熱によるものです(=食事誘発性熱産生)。この熱の量は栄養素の種類によって異なり、糖質だとエネルギー摂取量の5~10%といわれています(たんぱく質は20~30%、脂質は0~3%)。
また、食物繊維が多い食事を取ることで熱産生が増えるという報告もあります。上述の通り、冬野菜は糖質や食物繊維を多く含んでいるので、他の時期に旬を迎える野菜よりも消化吸収の過程で起こる熱産生が増えると考えられています。
冬野菜をおいしく食べて、からだぽかぽかに
大根やかぶ、ブロッコリーなどに多く含まれるビタミンCは、水に溶けやすい性質を持っているので、ゆで汁ごと食べられる“煮る”“蒸す”といった調理法がおすすめ。鍋料理や味噌汁、スープにすることで、素材のうま味も引き出せます。鍋にだしを取り、冷蔵庫にある冬野菜と豆腐、肉などを煮込むだけで、栄養素もうま味も余すことなく味わえる鍋・スープが完成します。
その他、しょうがや唐辛子などの香辛料には、血行を良くして代謝の活性化を促す成分が含まれています。麺類や汁物に加えるのも◎。そして、冬野菜の白菜も材料として使われている“キムチ”は手軽に取り入れやすい食材の一つです。ごはんのお供にはもちろん、うどんや鍋の味付けとして使うのもおすすめです。
からだにとって冷えは大敵。食事からも、冬に負けないからだづくりに取り組んでみませんか?
参考文献:
・~健康づくりサポートネット~,健康日本21アクション支援システム ,厚生労働省
https://kennet.mhlw.go.jp/slp/tools/web_learning/eat_chapter2
・冬に旬を迎える野菜って?,aff 2019年12月号,農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1912/spe2_01.html
・高田和子「調理科学とエネルギー代謝」日本調理科学会誌(J. Cookery Sci. Jpn.) Vol. 54,No. 3,125~131(2021)〔総説〕
https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/54/3/54_125/_pdf
タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?
タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。
ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。
- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
この記事はタメになりましたか?
人気記事ランキング
RANKINGあなたにおすすめの商品
人気記事ランキング
RANKING