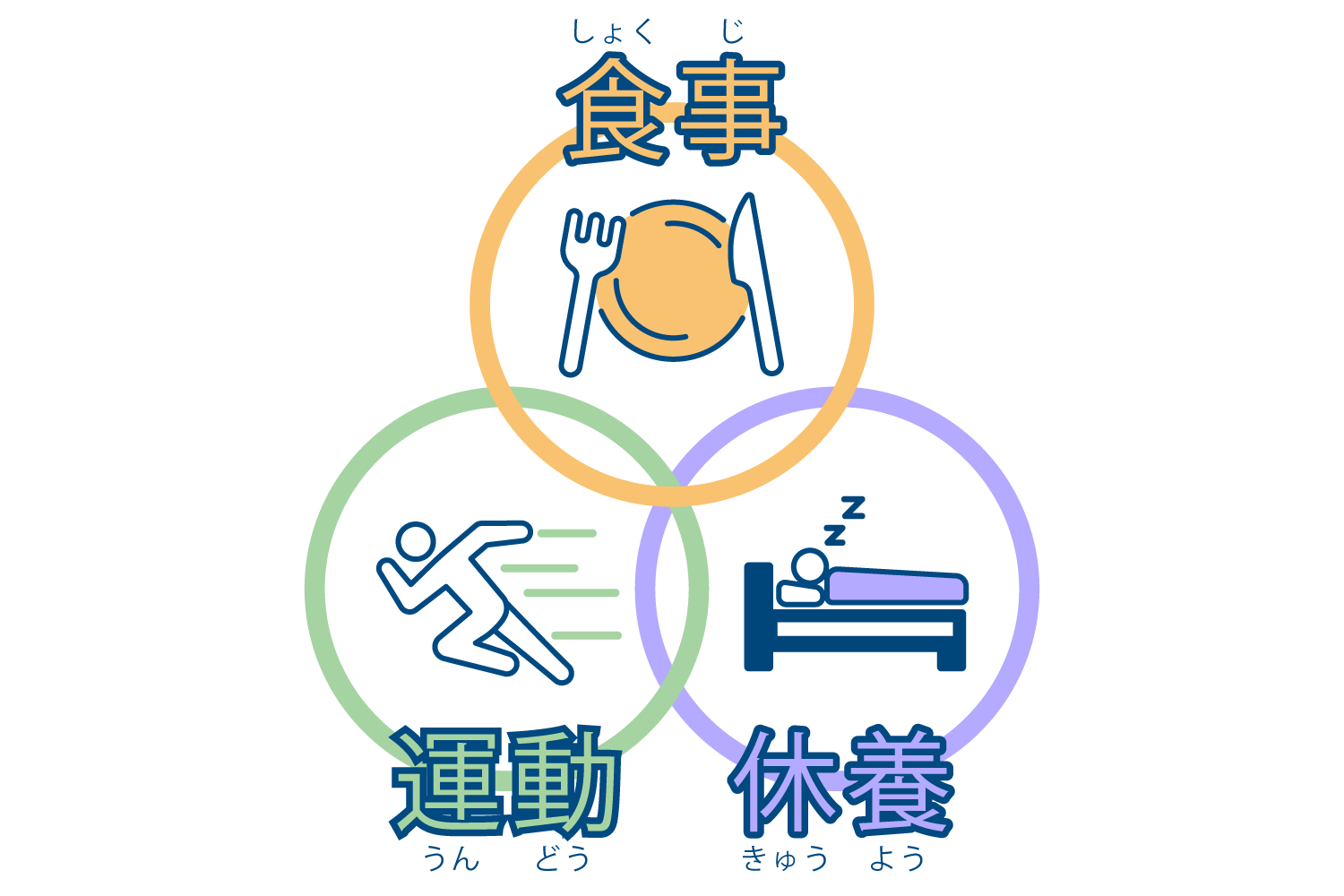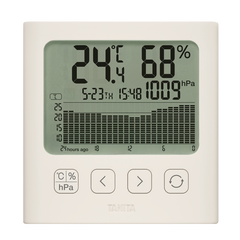タニタの考える健康
疲れがとれないあなたへ。休養の種類と特徴を知って心身を上手にケアしよう
2025.08.01

なんだかいつも疲れているような気がする。土日に休んだはずなのに疲れがとれない。 そんな悩みを「年齢のせい」「仕事は休めないから」と諦めていませんか? つらい疲れは、適切な休養をとることで解消できるかもしれません。今回は、休養の大切さや上手な休み方について、タニタの視点からご紹介します。
INDEX
プロフィール

株式会社タニタ 開発部/タニタ栄養研究所 堀越 理恵子
管理栄養士と公認スポーツ栄養士の資格を保有。グループ会社タニタヘルスリンクでのカウンセリング業務や健康セミナーの講師としての経験を経て、現在は株式会社タニタの開発部とタニタ栄養研究所に所属。プロアスリートやジュニア世代の食事やコンディショニングのサポートなどスポーツ支援を行っている。
「疲れ」の正体とは?
厚生労働省では、疲れを「身体的、あるいは精神的負荷によって活動能力が一時的に低下し、回復を必要とする状態」と定義しています。この定義をふまえると、ほとんどの現代人は疲れている状態といっても過言ではありません。
具体例を挙げると「朝すっきりと起きられない」「覚醒してからもからだが重だるい」などの状態は、疲労のサイン。また、普段は気にならないことにイライラするときは、心が疲れている可能性大です。
疲労回復にもつながる「健康3原則」
タニタでは、疲労の回復や軽減には食事・運動・休養の「健康3原則」が重要なポイントになると考えています。
なお、上記の3要素はどれかひとつが欠けただけでも健康維持に支障をきたします。必ず「3つを1セット」として意識してください。
「動的休養」が必要なのはどんなとき?
休養は「動的休養(積極的休養)」と、後述する「静的休養(消極的休養)」に大きく分けられます。
動的休養は、息が上がらない程度にからだを動かすことで疲労を回復させる休養方法。血流を改善して疲労物質や老廃物の排出を促したり、全身に酸素や栄養素を届けたりすることが疲労回復につながります。
さらに、適度に運動をすると自律神経の働きを整える「セロトニン」の分泌も促すため、心の休養にもつながります。
そんな動的休養は、以下のような疲れの解消に効果的です。
動的休養が必要なとき
- 激しい運動や長い立ち仕事で筋肉疲労がある
- 気分の落ち込みやストレスを感じている
- 座りっぱなしでからだの重さ、だるさを感じている
動的休養ってなにをすればいいの?
日常的にからだを動かす方にはヨガやジョギング、水泳などが動的休養として該当します。運動が苦手な方は、ストレッチやゆっくりとした散歩、もしくは日常生活の中でからだを動かす機会を増やすことから始めるのがおすすめです。
頻度としては、週に数回~毎日実践するのが理想的。生活スタイルや疲れの感じやすさには個人差があるので、「動的休養によってかえって疲れてしまった」ということがないよう、自分に合ったペースで実践してください。
「静的休養」が必要なのはどんなとき?
静的休養は、安静にすることで疲労を回復させる休養方法です。筋肉や神経、内臓などへの負荷を軽減し、脳をリラックス状態にします。さらに、副交感神経を優位にして、自律神経の働きを整える効果もあります。
とくに以下のようなケースでは、静的休養を優先してください。
静的休養が必要なとき
- 疲れがかなりたまっている
- 睡眠不足や風邪気味で体調が思わしくない
静的休養ってなにをすればいいの?
静的休養は、睡眠をとったり横になったりするほか、自分がリラックスできると感じる行動(読書や音楽鑑賞、瞑想、長すぎない入浴など)が該当します。
なお、なかなか寝つけない場合に「寝なければならない」と考えすぎると、かえって精神的負担につながることも。焦らずに過ごせるのであればベッドで横になって、焦りを感じるときは軽くストレッチをしたり、本を読んだり、温かい飲み物(カフェインやアルコールはNG)を飲んだりするのが効果的です。
ただし、部屋を明るくしすぎたり、スマホやパソコンを使用したりすると、脳が覚醒してしまうので注意が必要です。
静的休養の範囲は人によって異なる
一定以上の運動習慣がある方の場合は、先に「動的休養」でご紹介した、ヨガや軽いジョギングなども静的休養になりえる可能性があります。
静的休養の範囲は個人差が大きいので、生活習慣やからだの状態などをふまえて“自分にとって動的か静的か”判断してください。
「疲れをためないからだ」を目指す方法
疲れをケアせずに放置していると、メンタルを含めた不調、疾病のリスクが高まります。
また、疲労の度合いが高まるとリセットするのにも時間がかかるので、できるだけこまめに休養をとることが重要です。
一方で、日頃から「疲れをためないからだづくり」を目指すこともポイント。以下の点を意識しながら、食事・運動・休養の改善に取り組んでください。
1.食事のポイント
五大栄養素(炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラル)がバランスよく取れる食事を、朝昼夕の3回に分けて必要量食べましょう。主食・主菜・副菜に加えて、1日に1~2回は牛乳・乳製品や果物などを取り入れると、栄養バランスがより整いやすくなります。
なお、疲労回復の意味ではビタミンB1が豊富な「豚肉」やイミダゾールペプチド(イミダペプチド)を含む「鶏胸肉」を積極的に食べるのがおすすめです。
また、疲れているときは消化吸収に時間がかかる脂質の多い食材や揚げ物などは避けてください。
2.運動のポイント
息が弾む強度(心肺機能に負荷がかかる強度)の運動を、30分以上×週2回程度を目安に行ってください。
「自分にはハードルが高い」と感じる場合は、30分を15分×2回に分けるなど、細切れにしてもOKです。
3.休養のポイント
ライフサイクルや体調に合わせて動的休養や静的休養をとる習慣をつけましょう。
なお、必要な睡眠時間には個人差があります。一般的に成人であれば6時間以上がひとつの目安とされていますが、数字にこだわりすぎず、自分がすっきり目覚められる睡眠時間を見つけてください。
疲れているとジャンキーなものが食べたくなるのはなぜ?
疲労で脳がエネルギー不足の状態になると、からだは高カロリーな脂質や糖質を求めるように。
さらに、疲労やストレスを感じると体内で「コルチゾール(ストレスホルモン)」や「グレリン(空腹ホルモン)」が分泌され、その影響でも脂っこいものを欲しやすくなります。
そのため、疲れているとジャンキーなものを食べたくなるのです。
そんなときにおすすめなのが、夕食の「分食」。夕方に軽食を取ることで、遅い時間にジャンキーなものを食べる頻度を抑えやすくなります。どうしてもがまんできないときは、食後に活動時間が残っているお昼に食べるようにするといいですよ。
自分に必要な休養を知り、疲れを上手にケアしよう
私自身は休養の中でもとくに睡眠を重視しています。
睡眠の質を高めるために専門店で定期的に枕を調整したり、遮光カーテンを使って部屋を真っ暗にしたり、温湿度計を見ながらエアコンを調整したりと、過ごしやすい環境づくりを意識しています。
ちなみに、私がベストだと感じる睡眠時間は8時間程度。でも毎日8時間寝るのは難しいので、疲れてきたら予定をやりくりして8時間睡眠を目指したり、横になる時間も含めて8時間を確保したりしています。
みなさんも自分に必要な休養を見極めて、忙しい日々の中でも上手に心身をケアしてください。
タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?
タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。
ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。
- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
この記事はタメになりましたか?
人気記事ランキング
RANKING人気記事ランキング
RANKING